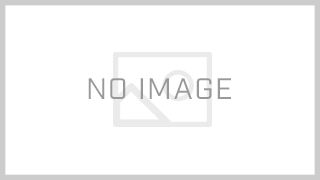お盆を過ぎるとあっという間にお正月が来ますね。お正月といえば「おせち料理」ですね。
おせち料理は、年神様をもてなすためのお供え料理で、近年は、年始に挨拶に来るお客様をもてなす料理とされています。
10月になれば各社おせちの予約が始まりますね。我が家では毎年、母親が手作りでおせち料理を作っていましたが、高齢になり作るのが億劫になったようで、今では毎年「ジャパネットたかた」で、おせち料理を予約しております。
ここでは、おせち料理の種類や意味について書いていきます。
おせちの種類
おせち料理は、大きく5種類あります。
✅祝い肴
✅口取り
✅焼き物
✅酢の物
✅煮物
おせち料理は、重箱に詰めるのが一般的です。「幸せを重ねる」という願いが込められているようです。正式には4段らしいですが、それぞれの段に何を詰めるかも決まっているようです。
一の重(祝い肴・口取り)
かまぼこ、伊達巻、数の子、黒豆、栗きんとんなど
二の重(焼き物)
鯛や鰤などの焼き魚、車海老など
三の重(酢の物)
紅白なますなど
与の重(煮物)
筑前煮など
おせちの意味
地域によって品数は違うようです。おめでたい意味が込められているようですので、代表的なものを紹介します。
もう20年も前になりますが、当時付き合っていた彼女が料理が大好きで、おせち料理も作ってくれました。ただ作るだけじゃなくて、以下に紹介するように1つ1つの意味もきちんと説明してもらったのが懐かしい思い出です。
黒豆
日焼けするほどマメ(元気)に働けるようにとの願いが込められているようです。
数の子
数の子はニシンの卵で、数が多いことから「数の子」と言われております。子孫繁栄を願う縁起物とされています。
きんとん
「金団」と書きます。金運を呼ぶ縁起物とされています。
伊達巻
形が巻物に似ており、知識が増えるようにとの意味があるようです。「伊達」は華やかさを表す言葉です。
昆布巻き
「こぶ」は「よろこぶ」に通じ、縁起物とされているようです。
鯛の姿焼き
「めでたい」の語呂合わせで、縁起物とされているようです。
車海老
茹でるとお年寄りのように腰が曲がります。その事から長寿でいられるようにとの意味が込められているようです。
ぶりの照り焼き
ぶりは出世魚として有名です。出世を願う縁起物とされているようです。
まとめ
豪華なおせち料理を前にすると「正月が来た」って実感できますよね。今ではデパートや料亭など各社様々なおせち料理を提供しています。内容量によっても金額は様々ですので、よく吟味してから予約するようにしたいですね。